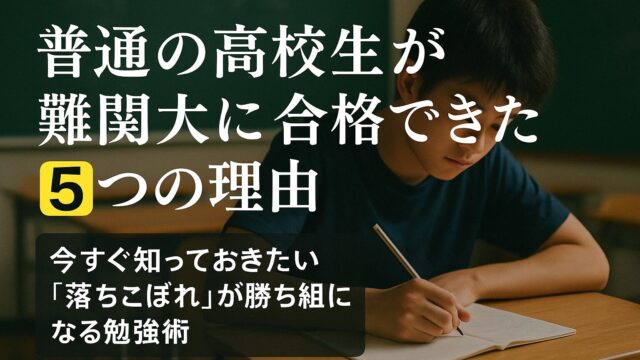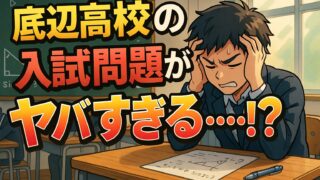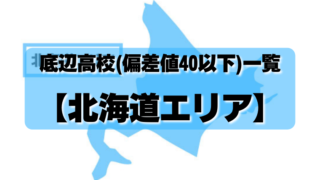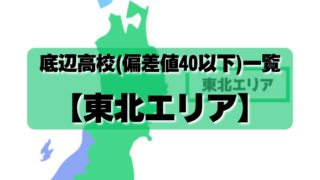「底辺高校にいるから、大学なんて無理だよ…」 そう思い込んで、将来をあきらめかけていませんか?
実は、偏差値40以下の高校からでも、難関大学への進学を実現した人はたくさんいます。
大切なのは、「今の偏差値」ではなく、「これからどう動くか」。
この記事では、実際に底辺高校と呼ばれる学校から大学に進学した人たちのリアルな体験談や、逆転のために実践した勉強法、そして成功の秘訣を5つ紹介します。
底辺高校からでも大学進学は可能!その理由と背景を解説

「底辺高校から大学進学なんて無理だよ」
──そう言われてしまうのはなぜなのでしょうか?
結論から言えば、それは“環境”と“思い込み”のせいです。
実際には、近年の大学入試制度の変化や学習環境の進化により、どんな高校に通っていようと本人の努力次第で十分逆転できる時代になっています。
この章では、底辺高校からの進学が難しいと言われる背景と、なぜ今なら可能性が広がっているのかを詳しく解説していきます。
なぜ「底辺高校は進学できない」と言われるのか?
授業レベルや進学指導の差
底辺高校では、授業内容が基本〜標準レベルにとどまっており、大学受験に対応した演習や対策が少ない傾向にあります。
また、進学実績が乏しいため、教師も大学受験に詳しくないことがあり、生徒がどのように受験を戦えばいいかを明確に指導できないケースが多いのです。
周囲のモチベーションの低さ
「進学なんて考えていない」という生徒が大多数を占める場合、真剣に勉強しようとする生徒も、浮いてしまったり、やる気を保ちにくくなったりします。
環境によって、頑張る人ほど孤独になりやすいのが底辺高校の現実です。
学力以前の「自信のなさ」も大きな要因
「どうせ自分には無理だ」「うちの学校じゃ無理」といった、自己肯定感の低さや周囲の否定的な言葉が、進学の意思そのものを曇らせてしまいます。
しかし、これは裏を返せば、“自信さえ持てれば”環境に関係なく挑戦できるということでもあります。
今どきの大学入試事情はどう変わっている?
共通テストの比重低下と多様化
国公立大学を中心に導入されている「大学入学共通テスト」は、かつてのセンター試験よりも思考力・判断力を問う問題が増え、暗記だけでは通用しない傾向に。
一方で、私立大学では共通テスト利用入試を廃止・縮小する動きも見られ、個別試験や推薦型入試に比重を移す大学も増えています。
推薦・総合型選抜が拡大中
最近では、学校推薦型選抜(指定校・公募)や総合型選抜(旧AO入試)を導入する大学が増加。
学力試験よりも、面接や志望理由書、活動実績を重視する傾向が強く、学力に自信がない人でも準備次第で合格が狙えます。
オンライン塾や映像授業の普及で差が縮小
今では、スタディサプリやYouTube講義など、誰でも質の高い授業を無料・格安で受けられる時代です。
底辺高校にいても、自宅で進学校並みの学習を積むことが可能になり、学力差を自分で埋められる環境が整っています。
底辺高校から大学進学した5つの成功実例を紹介

実例① 偏差値42から関関同立へ!塾なし逆転合格
中学レベルの英数を徹底復習
まずは中学の教科書からやり直し。
特に英語と数学は、基礎の抜けが致命的になるため、教科書+ワークを繰り返しました。
YouTubeとスタディサプリを駆使
塾に通う余裕がなかったため、スタディサプリ(月2,000円台)とYouTube講義を徹底活用。(【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座)
![]()
プロ講師の授業を何度も見直すことで、学校の授業の穴を埋めました。
先生に頼らず自分で調べて動いた
進学指導が不十分だったため、自分で大学情報を集め、赤本(過去問)を早期に入手して分析。
「知らないことは全部ググる」が彼の口癖だったとか。
実例② 高3の夏から猛勉強してMARCH合格
夏まで部活漬け、そこから年末まで毎日8時間
高3の夏までバスケ部で活動していた男子生徒。
引退後すぐに「これじゃヤバい」とスイッチが入り、1日8時間以上の勉強を半年間継続。
志望理由書と面接対策も一人で研究
総合型選抜(旧AO)を利用。
志望理由書は10回以上書き直し、先生に添削をお願い。面接練習はスマホで自撮りして改善したという努力派。
親の反対を説得して受験に挑んだ話
「ウチの学校からじゃ無理」と言われ、親も最初は反対。
でも結果が出始めた秋頃には応援モードに。“やってる姿を見せる”ことで周囲を変えた好例です。
実例③ 通信制高校から国立大学に編入成功
2浪して同志社→神戸大編入のリアル
偏差値が低い高校から通信制に転校。
2年間の浪人を経て同志社に合格し、その後3年次編入で神戸大学へ進学。執念のストーリー。
再受験の覚悟と環境づくり
アルバイトをしながらの再挑戦だったが、毎朝6時起き・夜は図書館で勉強の生活を継続。
SNSで同じ境遇の仲間と励まし合った。
学び直しのプラットフォーム活用
「学び直し」がキーワード。
スタディサプリやmanaba、東進の過去講義など社会人向け教材も活用し、時間のロスを最小限に抑えた。
実例④ 偏差値38の高校から地方国立大学へ
進学校じゃなくてもコツコツ継続
学年で大学志望者はたった3人。
その中で誰よりもコツコツ型の勉強を選び、最後は推薦ではなく一般入試で勝負。
学校外の先生やSNSのつながりが支えに
TwitterやYouTubeで受験アカウントを活用し、情報収集とメンタルサポートを確保。
孤独を乗り越えた工夫が光りました。
勉強法より「習慣化」の重要性
毎日1時間でいいから必ず机に向かう。
その“リズムを守ること”が最大の要因だったと、後に語っています。
実例⑤ 不登校経験者が通信制→私大合格まで
高校在籍中にN高の映像授業で自習
学校に通えない時期が長かったが、N高の映像授業で自分のペースを確立。
学力の穴を埋め、意欲も徐々に回復。
自己分析と目標設定で勉強に目覚める
「なぜ勉強するのか」を明確にするために、大学で何を学びたいか、どんな仕事に就きたいかを紙に書き出した。
目的ができてから勉強が楽しくなったそう。
メンタルと向き合ったからこそ結果が出た
不登校という過去に負けないために、カウンセリングや読書を通じて“自己受容”を育んだ。
精神面の強さも合格を後押しした大事な要素でした。
進学するための3つの重要ステップと成功のコツ
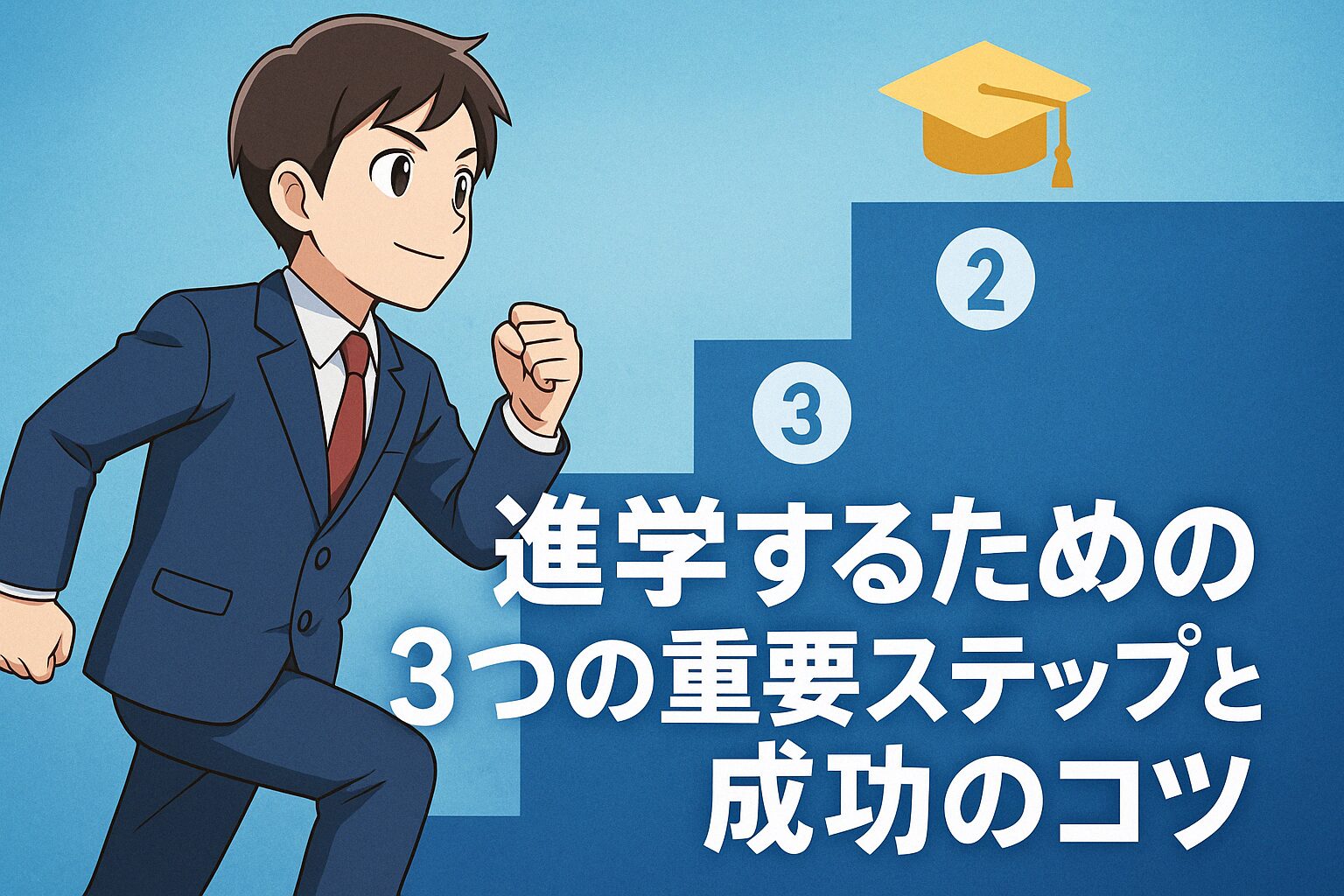
① 中学レベルの基礎固めが最優先
英語・数学・国語の復習スケジュール例
まずは「できない」原因を潰すことが重要。
中学の教科書レベルが理解できていないと、高校の内容はまったく歯が立ちません。
特に英語と数学は連続性が高い科目なので、中1から順を追って復習するのがポイントです。
おすすめスケジュール(1日30分×3教科)
- 1週目:英単語・計算ドリル・漢字練習
- 2週目:英文法の基礎・一次方程式・古文単語
- 3週目:英語長文(中学レベル)・関数・読解演習
市販教材・無料サービスの選び方
独学には教材選びが超重要。難しすぎず、繰り返しやすいものを選ぶのがコツです。
- 英語:「くもんの英語ドリル」「中学英文法をひとつひとつわかりやすく」
- 数学:「大人のためのやり直し中学数学」「高校入試の基礎から始める」
- 無料サービス:「スタディサプリ」「Try It」「YouTube:とある男が授業してみた」
「自分はできない」と思わない工夫
「やっぱり無理かも…」と思う瞬間は必ず来ます。
そんなときは、成功した人の体験談やコメントを読み返すこと。
目標を紙に書いて、机の前に貼るのも効果的です!
② 情報収集と戦略設計で周囲と差をつける
志望校選びと入試方式の見極め方
今の成績だけで大学を選ばないでください。
推薦・総合型選抜・共通テスト利用など、入試方式は多様化しています。
まずは「どんな入試方式が自分に向いているか」を調べましょう。
- 「大学案内サイト」「パスナビ」「スタディサプリ進路」で志望校リサーチ
- 総合型選抜や推薦は「過去の合格者レポート」もチェック
進学ブログ・SNSで実例から学ぶ
「偏差値40から合格」などのキーワードで検索すれば、似た境遇の人のリアルな体験談が見つかります。
ブログ・note・X(旧Twitter)などを活用して、生の声から学ぶ習慣を。
総合型選抜や推薦枠の活用法
評定平均が3.0以上ある場合、公募推薦や指定校推薦の対象になる可能性があります。
また、活動実績(部活・ボランティア・資格など)をまとめておくと総合型選抜で有利です。
③ 習慣化とメンタルケアが長期戦の鍵
1日30分から始める習慣づくり
「いきなり3時間は無理…」
そんな人は、まずは毎日30分だけ机に向かう習慣から。
“やる日”ではなく“やらない日を作らない”のがポイントです。
ポジティブな言葉と人間関係の大切さ
「自分にはできる」
「今の努力が未来をつくる」
こうした言葉を自分自身にかけ続けることで、自信と集中力は必ず育ちます。
可能であれば、応援してくれる大人や友達と関わることも大切です。
「折れない心」をつくる自己対話
模試の結果が悪くても、思うように進まなくても、それは“未来をあきらめる理由”にはなりません。
「今日はできなかった。でも明日はやる」
そんな自分との対話を毎日続けることで、芯の強さが生まれてきます。
出身高校は関係ない。未来を変えるのはあなた自身
偏差値が低い高校に通っているからといって、あなたの未来が決まってしまうわけではありません。
大学進学に必要なのは、「今の環境」よりも「これからどう動くか」。
この記事で紹介したように、底辺高校からでも大学に進んだ人はたくさんいます。
彼らがやったことは、特別な才能ではなく、基礎をやり直し、自分に合った方法を見つけて、コツコツ続けたということ。それだけなんです。
周りに「無理」と言われても、学校で放置されても、自分さえあきらめなければ、道は必ずあります。
あなたの一歩が、未来を変えるスタートになります。